スイッチボット 何が必要?ハブ3と必須環境まとめ|まずはハブ導入から

スイッチボットでスマートホーム化したいけれど、「いったい何が必要なの?」「どれから買えばいいか分からない」と迷っていませんか?この記事では、スマートホーム化の第一歩として、スイッチボット 何が必要か、その基本を徹底的に解説します。まず、スイッチボット とは何か、その基本機能から見ていきましょう。「スイッチボット いらない?」という声も聞かれますが、それは多くの場合、製品の真価を引き出す「あるモノ」の役割を理解していない誤解かもしれません。スマート化の核となる絶対必要なハブについて、現行の3種類を比較します。その上で、なぜ結論としておすすめはハブ3なのかを具体的に説明し、導入前の必須環境であるWi-Fi 2.4GHzの確認方法にも触れます。さらに、ハブ導入後スイッチボット 何が必要か、定番アイテムのボットとは何か、ハブ購入後 ボットでできること、そして思わず試したくなるボットの面白い 使い方を紹介します。最終的なスマートスピーカーと連携が理想形となる快適な使い方や、導入前に知るべき危険性も隠さずお伝えします。この記事を読めば、あなたにとってスイッチボTfット 何が必要かの結論が明確になるはずです。
- スイッチボットの基本的な仕組みとスマート化の核となる役割
- スマートホーム化に「ハブ」が絶対に必要な理由
- 現行ハブ3機種(ハブミニ・ハブ2・ハブ3)の具体的な違いと選び方
- ハブ導入後に買い足すべきおすすめ定番製品とその活用法
スイッチボット 何が必要?基本を解説
- スイッチボット とは?基本機能
- スイッチボット いらない?は誤解
- 絶対必要なハブ 3種類を比較
- 結論としておすすめはハブ3
- 必須環境Wi-Fi 2.4GHzの確認
スイッチボット とは?基本機能
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージスイッチボット(SwitchBot)とは、SWITCHBOT株式会社が提供しているスマートホーム家電製品の総称です。これらの製品群の最大の魅力は、既存の家電や設備を買い替えることなく、まるでDIYのように「後付け」するだけで、簡単に家全体をスマートホーム化できる点にあります。
例えば、壁にある照明の物理スイッチ、エアコンやテレビのリモコン、毎日開け閉めするカーテンレールなど、本来はインターネットとは無縁だったものにSwitchBot製品を取り付けることで、スマートフォン(スマホ)の専用アプリから一括で操作できるようになります。
多くの製品が持つ基本的な機能は、専用アプリを通じた「Bluetooth(ブルートゥース)接続」による直接操作です。スマホとデバイス(ボットやカーテンなど)がBluetoothの電波が届く範囲(製品によりますが、見通しの良い場所で約10m〜80m程度)にあれば、アプリから直接オン・オフの指示を送れます。例えば、ベッドの中からリビングの照明スイッチに取り付けたボットを操作する、といった使い方が可能です。
しかし、SwitchBotの真価は、後述する「ハブ」製品と連携させることで発揮されます。ハブは、家中のSwitchBot製品と自宅のWi-Fiルーターとを繋ぐ「司令塔」の役割を果たします。ハブを介してWi-Fiに接続することで、Bluetoothの範囲外、すなわち外出先からの遠隔操作(例:帰宅前にエアコンをつける)や、Amazon Alexa(アレクサ)やGoogle Homeなどのスマートスピーカーを通じた音声操作(例:「アレクサ、テレビ消して」)、さらには製品同士の連携(例:「温湿度計が30度になったら、自動でエアコンをオンにする」)といった、本格的なスマートホーム機能が利用可能になります。
スイッチボット いらない?は誤解
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージ「スイッチボット いらない」あるいは「買ってみたけど期待外れだった」という意見を見かけることがありますが、これは多くの場合、製品の特性、特に「ハブ」の重要性を十分に理解していないことによる誤解から生じています。
確かに、SwitchBotボット(指ロボット)やSwitchBotカーテン、SwitchBot温湿度計などの人気製品は、単体でもBluetooth接続だけで動作します。そのため、「お試しでボットだけ買ってみた」という方も少なくありません。家の中でスマホアプリを立ち上げ、Bluetoothの接続範囲内でカーテンを開閉したり、ボットでスイッチを押したりすることは可能です。
しかし、この使い方だけでは「スマートホーム」と呼ぶには機能が限定的すぎます。わざわざスマホを取り出し、アプリを起動し、デバイスに接続する…という手順は、時に手でスイッチを押すよりも面倒に感じることさえあります。ハブがない状態では、以下のようなスマートホームの核となる機能が一切使えません。
ハブが無い場合の主な制限
- 外出先からの操作ができない:ペットのためにエアコンをつけたい、電気を消し忘れたかも、と思っても家に戻るしかありません。
- スマートスピーカーによる音声操作ができない:「アレクサ、電気つけて」といったハンズフリー操作が一切できません。
- 製品同士の自動連携ができない:「温度が上がったらエアコンをつける」「ドアが開いたら照明をつける」といった自動化が組めません。
「いらない」と感じる人の多くは、ハブを導入せず、Bluetoothのみの限定的な機能で「こんなものか」と満足できなかったケースが考えられます。SwitchBotの便利な機能を100%フル活用するためには、司令塔であるハブの存在が不可欠です。したがって、「いらない」のではなく、「SwitchBotの真価を発揮させるためには、ハブが必要」と理解するのが正しいと言えます。
絶対必要なハブ 3種類を比較
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBot製品群を自宅のWi-Fiに接続し、その能力を最大限に引き出すために「絶対必要なハブ」は、まさにスマートホーム化の司令塔(コントロールセンター)です。ハブには大きく分けて3つの重要な役割があります。
- スマートリモコン機能:エアコン、テレビ、扇風機、照明など、赤外線リモコンで操作する旧来の家電のリモコン情報をハブに学習させることができます。これにより、家中のリモコンをスマホアプリや音声操作に集約できます。
- SwitchBot製品の橋渡し(ゲートウェイ機能):Bluetoothでしか通信できない個々のSwitchBot製品(ボットやカーテン、センサー類)をハブが取りまとめます。ハブがBluetooth通信をWi-Fi通信に変換することで、各デバイスがインターネットに接続可能になります。
- スマートスピーカー・外部サービス連携:Amazon Alexa、Google Home、Siri(Apple HomeKit)といったスマートスピーカーや、IFTTT(イフト)などの外部サービスと連携し、音声操作やより高度な自動化を実現するための窓口となります。
現在、主流となっているハブ製品は以下の3種類です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の環境に合ったものを選ぶことが大切です。
| 機能・製品名 | SwitchBot ハブミニ (Matter対応版) | SwitchBot ハブ2 | SwitchBot ハブ3 |
|---|---|---|---|
| スマートリモコン | ◯
(基本的なリモコン操作) |
◯
(ハブミニより赤外線送信範囲が広い) |
◯
(赤外線性能・登録数が最強レベル) |
| 温湿度計・照度計 | ×
(別途センサーが必要) |
◯
(高精度センサーと画面表示あり) |
◯
(高精度センサーと画面表示あり) |
| スマートボタン | × | ◯
(2個搭載・シーン実行に便利) |
◯
(画面にタッチボタン搭載) |
| 直感的操作 | ×
(スマホ・音声のみ) |
×
(スマホ・音声・本体ボタンのみ) |
◯
(ノブ型コントローラー) |
| Matter対応 | ◯
(子機としてのみ) |
◯
(ハブとして機能) |
◯
(ハブとして機能) |
| 特徴 | シンプル・安価。
まずはスマートリモコン機能と連携を試したい方向け。 |
センサーとボタンが一体化。
環境に応じた自動化も組みたい、高コスパな中核モデル。 |
全機能搭載+唯一のノブ操作。
最も高機能で快適さも追求した最上位モデル。 |
※Matter(マター)とは、異なるメーカーのスマートホーム製品同士を連携させるための共通規格です。ハブ2やハブ3はMatterに対応しており、将来的な拡張性が高い点も魅力です。
結論としておすすめはハブ3
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージ前述の比較を踏まえ、「スイッチボット 何が必要」という問いに対する最初の答えとして、自信を持って最もおすすめしたいのは、最上位機種の「SwitchBot ハブ3」です。
理由は複数あります。第一に、ハブ2が持つ「高精度な温湿度計・照度センサー」や「スマートボタン」といった便利な機能をすべて網羅している点です。部屋の温度や湿度、明るさを正確に把握し、それをトリガー(引き金)にして「暑くなったらエアコンON」「暗くなったら照明ON」といった自動化を組む上で、これらのセンサー類は非常に役立ちます。
第二に、「司令塔」としての基本性能が圧倒的に高い点です。赤外線の学習能力や送信性能が従来機(ハブミニ、ハブ2)より大幅に向上しています。これにより、古い家電やマイナーなメーカーのリモコンでも登録できる成功率が格段に上がり、「せっかく買ったのにリモコンが登録できなかった」という失敗を最小限に抑えられます。
そして最大の理由は、ハブ3独自の「ノブ型(ダイヤル式)コントローラー」の存在です。スマートホーム化を進めると「エアコンの温度を1度だけ下げたい」「照明を少しだけ暗くしたい」といった微調整のシーンが必ず出てきます。そのたびにスマホアプリを開いたり、スマートスピーカーに正確な指示で話しかけたりするのは、時に煩わしく感じることもあります。ハブ3なら、本体のノブを回す・押すといった直感的な操作だけで、照明の明るさ、エアコンの温度、カーテンの開閉率などをシームレスに微調整できます。この「直感的な操作性」が、日々の生活における「小さなストレス」を確実に減らし、快適さを格段に向上させます。
初期費用こそ他のハブより高くなりますが、これから本格的にスマートホームを構築する上で、機能性、操作性、そして将来的な拡張性のすべてにおいて、ハブ3を選ぶことが最も満足度の高い選択になると考えられます。
必須環境Wi-Fi 2.4GHzの確認
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBotハブ製品(ハブミニ、ハブ2、ハブ3)をセットアップする上で、絶対に欠かせない必須環境が「2.4GHz(ギガヘルツ)帯のWi-Fi」です。
現在、家庭用のWi-Fiルーターには主に「2.4GHz」と「5GHz」という2つの周波数帯があります。それぞれの特性を理解しておくことが重要です。
2.4GHzと5GHzの主な違い
- 5GHz帯
- 特徴:通信速度が非常に速い。電波干渉が少ない。
弱点:壁や床、家具などの障害物に弱く、電波が遠くまで届きにくい。
- 2.4GHz帯
- 特徴:障害物に強く、壁越しや別室など遠くまで電波が届きやすい。
弱点:通信速度は5GHzに劣る。電子レンジやBluetoothなど他の機器と電波干渉しやすい。
SwitchBot製品を含む多くのスマートホーム機器(IoT機器)は、通信速度よりも「家中に安定して電波を届かせること」を重視するため、障害物に強い「2.4GHz帯」を採用しています。(参考:総務省 電波利用ホームページ「無線LANの基礎知識」)
そのため、ハブをWi-Fiに接続設定する際は、お使いのスマートフォンを必ず2.4GHz帯のネットワークに接続してから作業を行う必要があります。
ご自宅のWi-Fi環境の確認方法
ご自宅のWi-Fiルーターが2.4GHzに対応しているか確認するのは簡単です。まず、ルーターの本体側面や底面に貼られているラベル(シール)を見てください。そこにネットワーク名(SSID)が記載されています。
多くの場合、2.4GHz帯と5GHz帯でSSIDが分かりやすく分けられています。
- 2.4GHz帯のSSID例: 「MyRouter-2G」 「MyRouter-g」
- 5GHz帯のSSID例: 「MyRouter-5G」 「MyRouter-a」
SwitchBotアプリでセットアップを行う際は、スマートフォンのWi-Fi接続先を、この「-2G」や「-g」がついた2.4GHz帯のネットワークに切り替えてから作業を進めてください。もし5GHz帯のネットワークに接続したまま設定しようとすると、エラーとなり接続が完了しないため注意が必要です。
※最近のルーター(メッシュWi-Fiなど)に関する注意点:
最近は「バンドステアリング」という機能により、2.4GHzと5GHzのSSIDが1つに共通化されているルーターも増えています。この場合、スマホが自動的に5GHz帯に接続してしまい、設定がうまくいかないことがあります。その際は、ルーターの管理画面から一時的に5GHz帯の電波をオフにするか、2.4GHz帯と5GHz帯のSSIDを分離する設定に変更する必要があります。
ハブ導入後スイッチボット 何が必要か
- 定番アイテムのボットとは
- ハブ購入後 ボットでできること
- ボットの面白い 使い方を紹介
- スマートスピーカーと連携が理想形
- 導入前に知るべき危険性
定番アイテムのボットとは
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージハブを導入し、スマートホームの「司令塔」を設置した次に必要となるアイテムとして、最も定番で人気が高いのが「SwitchBot ボット」です。これは、その名の通り「ロボット」であり、人間の指の代わりに物理的なボタンやスイッチを代わりに押してくれる「指ロボット」と呼ばれる製品です。
本体から小さなアーム(腕)が突き出すシンプルな仕組みになっており、アプリから操作すると、そのアームがウィーンと動いてスイッチを押します。設置は驚くほど簡単で、押したいスイッチの近くに付属の強力な両面テープで貼り付けるだけです。壁に穴を開けたり、配線をいじったりといった工事や工具は一切必要ありません。
ボットには主に2つの動作モードが用意されています。
- 1. 押すモード
- アームがスイッチを「押す」だけのシンプルな動作です。電源オンとオフが1つのボタンで切り替わる家電(例:空気清浄機、扇風機、コーヒーメーカー、お風呂の湯沸かしボタンなど)に適しています。
- 2. スイッチモード
- 「オン」と「オフ」が物理的に分かれているシーソー式・ロッカースイッチ(例:壁の照明スイッチ)に対応するモードです。付属の小さなパーツ(先端に糸が付いたシール)をスイッチの「オフ側」に貼り付けます。ボットは「押す」動作でオンにし、「アームを引き戻す」動作で糸を引っ張り、スイッチをオフ側に倒します。
このように、赤外線リモコンがなく、スマート化を諦めていたような古い家電や住宅設備であっても、このボットを使えば簡単にスマートホームの仲間入りをさせることが可能です。
ハブ購入後 ボットでできること
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBot ボットは、前述の通りハブがなくてもBluetoothの範囲内であればスマホアプリから直接操作できます。しかし、ハブと連携させる(ハブにボットを登録する)ことで、その可能性は飛躍的に広がります。
第一に、外出先からの遠隔操作が可能になります。
これがハブを導入する最大のメリットの一つです。例えば、暑い日に会社から帰宅する少し前に、ハブを経由してボットに指示を送り、お風呂の湯沸かしボタンを押させておくことができます。帰宅後すぐにお風呂に入ることが可能です。また、「玄関の電気、消し忘れたかも?」と不安になった時も、外出先からアプリでボットを操作して確実にオフにできます。
第二に、スマートスピーカーによる音声操作です。
「アレクサ、リビングの電気をつけて」と声をかけるだけで、アレクサがインターネットを通じてハブに指示を出し、ハブがBluetoothでボットに「壁のスイッチを押す」よう命令します。料理中で手がふさがっている時や、布団に入ってから「あ、電気消し忘れた」と気づいた時に、ベッドから出ることなく音声で操作できる快適さは格別です。
第三に、他のSwitchBot製品との連携(自動化)です。
ハブは、異なるデバイス間の「橋渡し」として機能します。例えば、「SwitchBot 温湿度計」が室温30度を検知したら、ハブを通じてボットに指示が飛び、ボットが扇風機の電源ボタンを押す、といった設定ができます。ほかにも「SwitchBot 開閉センサー」と連携し、「ドアが開いたら、ボットが玄関の照明スイッチを押す」といった自動化も可能です。
ボットの面白い 使い方を紹介
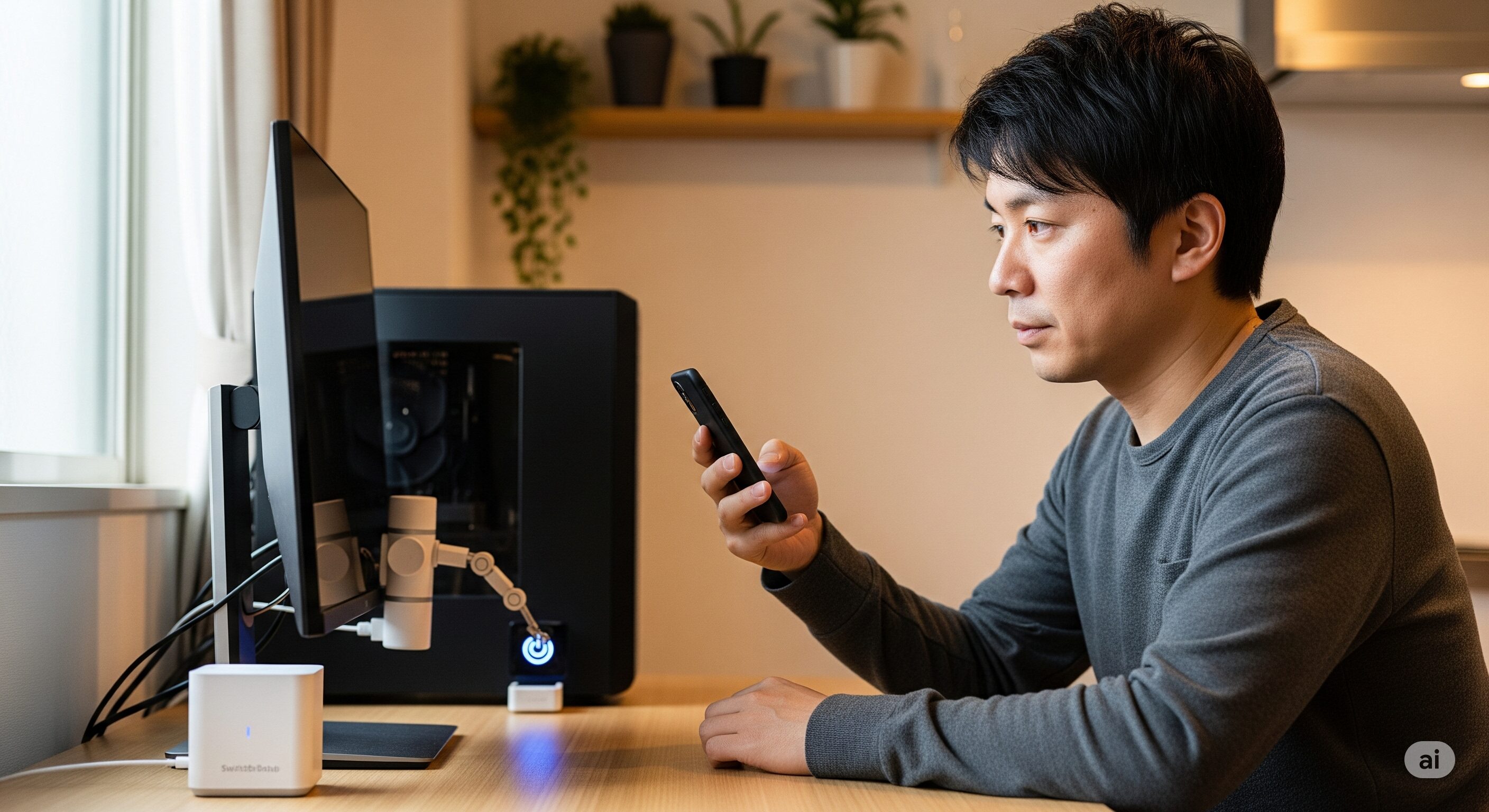 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBot ボットは、「物理的にスイッチを押す」という非常にシンプルな機能ゆえに、ユーザーのアイデア次第で驚くほど多様な「面白い使い方」が可能です。以下に、定番から少し変わったものまで、いくつかの活用例を紹介します。
SwitchBot ボット活用アイデア例
- リモコンのない家電の操作:空気清浄機、加湿器、扇風機、除湿機など、電源ボタンしかない家電の操作に最適です。タイマー機能のない機種でも、ボットで時間制御が可能になります。
- コーヒーメーカーや電気ケトルの起動:朝起きる時間に合わせてボットがコーヒーメーカーのスイッチを押すようにスケジュール設定しておけば、目覚めと同時に淹れたてのコーヒーができあがっています。
- 別室のプリンターやPCの電源:普段は電源を切っているプリンターやデスクトップPCの電源ボタンに設置。印刷したい時やリモートデスクトップ接続したい時だけ、自室からボットで電源をオンにするといった使い方が便利です。
- 換気扇のスイッチ:トイレやキッチンの換気扇スイッチ(タイマーなし)に設置し、「1時間後に自動でオフにする」ように設定すれば、無駄な電力消費と消し忘れを防げます。
- ガレージのシャッターボタン:屋内の壁にあるガレージシャッターの開閉ボタンに設置し、車が近づいたらスマホで操作する、といった活用もされています。
- ルーターの再起動ボタン:Wi-Fiの調子が悪い時に、物理的に電源を抜き差しするのが面倒なルーターの再起動(リセット)ボタン用として設置する猛者もいます。
- インターホンの解錠ボタン(※要注意):マンションのオートロック解錠ボタンに設置する例もあります。ただし、これは物理的に誰でも解錠できてしまう状態になるため、設置場所のセキュリティ(部屋の内側からのみアクセスできるかなど)には細心の注意が必要です。
このように、単純に「押す」という動作だけで、日々の生活における「ちょっとした手間」を劇的に削減できるのがボット最大の魅力です。
スマートスピーカーと連携が理想形
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBot製品(ハブ、ボット、カーテン、センサー類)を導入し、スマートホーム化を進める上で、最終的に目指したい「理想形」は、やはりスマートスピーカーとのシームレスな連携です。
Amazon Alexa(Echoシリーズ)や Google Home(Google Nestシリーズ)、Apple HomePod(Siri)といったスマートスピーカーとSwitchBotハブを連携させることで、あらゆる操作が「声」だけで完結する、ハンズフリーの快適な生活が実現します。
「アレクサ、テレビをつけて」「OK Google、エアコンを26度にして」「Siri、カーテンを開けて」といった個別の家電操作はもちろんですが、スマートホームの真価は「シーン」や「定型アクション」と呼ばれる、複数の操作をまとめた自動化にあります。
例えば、SwitchBotアプリやアレクサアプリで「いってきます」というシーン(定型アクション)をあらかじめ設定したとします。朝、玄関に向かいながら「アレクサ、いってきます」と一言告げるだけで、ハブが司令塔となり、以下の操作を一度に(あるいは順番に)実行します。
「いってきます」シーンの実行例
- リビングのテレビを消す(ハブのスマートリモコン機能)
- エアコンを消す(ハブのスマートリモコン機能)
- リビングと寝室の照明を消す(ボットが壁スイッチを押す)
- すべてのカーテンを閉める(SwitchBotカーテンが動作)
- ロボット掃除機(対応機種の場合)の清掃を開始する
同様に、「おはよう」と声をかければ、カーテンが自動で開き、照明がつき、テレビでニュースが流れる、といった設定も可能です。このように、ハブを司令塔としてスマートスピーカーと連携させることで、日々のルーティンワークや家電操作の手間が最小限になり、ワンランク上の快適なスマートライフが完成します。
導入前に知るべき危険性
 パーシーのガジェブロイメージ
パーシーのガジェブロイメージSwitchBotは非常に便利で生活を豊かにする製品ですが、インターネットに接続するIoT機器である以上、導入する前にはいくつかの注意点、いわゆる「危険性」や潜在的なリスクについても正しく理解しておく必要があります。
1. サイバーセキュリティのリスク
SwitchBotハブは、家のWi-Fiを通じて常にインターネットに接続されます。これは、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃、アカウント乗っ取りのリスクがゼロではないことを意味します。万が一、ハブやアカウントが乗っ取られると、家電を勝手に操作されたり、もしSwitchBot製の屋内カメラを設置している場合は、室内の映像を盗み見られたりする危険性があります。
対策:SwitchBotアカウントのパスワードは、他のサービスと使い回さず、類推されにくい複雑なものに設定することが不可欠です。また、自宅のWi-Fiルーターのセキュリティ機能(ファームウェアの自動アップデートなど)を常に最新の状態に保つことも重要です。
2. 物理的なトラブルと相性(特にボット)
特にSwitchBot ボットは物理的に動作するため、設置対象との「相性」が存在します。押したいボタンが極端に小さい、深く凹んでいる、静電容量式のタッチセンサー(軽く触れるだけのタイプ)である場合、ボットのアームがうまく押せず、期待通りに動作しないことがあります。また、一部のパソコンの電源ボタンのように、数秒間の「長押し」が必要なスイッチも苦手な場合があります。
対策:導入前に、設置したい場所のスイッチ形状や、どのような押し方(軽く押す、深く押す、長押しなど)が必要かをよく確認することが大切です。
3. 遠隔操作の過信による火災リスク
これが最も注意すべき重大な危険性です。外出先から家電を操作できるのは非常に便利ですが、製品の特性上、絶対に遠隔操作してはならない家電が存在します。
警告:遠隔操作による火災の危険性
電気ストーブ、電気コンロ、こたつ、ヘアアイロン、電気ポット、電気ケトルなど、熱を発する電熱器具の遠隔操作は絶対に行わないでください。
もし遠隔で電源をオンにした際、その家電の近くに衣類や紙類、カーテンなどの燃えやすいものがあった場合、火災を引き起こす深刻な危険性があります。
NITE(製品評価技術基盤機構)も、遠隔操作やタイマー設定による電熱器具の事故に対して厳重な注意喚起を行っています。(参考:NITEプレスリリース「その一手間が、火事を防ぐ」)
これらの家電の操作は、必ず目の届く安全な状況でのみ行ってください。
4. ネットワーク環境への完全依存
SwitchBotの便利な機能(遠隔操作、音声操作、自動化)はすべて、自宅のWi-Fi環境とインターネット回線に100%依存しています。もし停電やWi-Fiルーターの不具合、プロバイダの通信障害などでインターネットが停止すると、ハブが機能しなくなり、すべてのスマート機能が一時的に利用不能になります。
対策:あくまで「便利な付加機能」と捉え、万が一Wi-Fiがなくても、従来通り手動でスイッチを押したり、リモコンで操作したりできる状態は必ず維持しておくことが賢明です。スマート化によって物理スイッチが操作不能になるわけではないので、過度に心配する必要はありませんが、依存しすぎない心構えも大切です。
スイッチボット 何が必要かの結論
この記事で解説してきた「スイッチボット 何が必要か」についての要点を、結論として以下に箇条書きでまとめます。スマートホーム化の第一歩として、これらのポイントを押さえておきましょう。
- スイッチボットは既存の家電や設備に「後付け」でスマート化する製品群
- スマート化の核となる「司令塔」として「絶対必要なハブ」がまず必要になる
- ハブがない状態では遠隔操作や音声操作、製品同士の連携が一切できない
- ハブはエアコンやテレビなど赤外線家電のスマートリモコンの役割も果たす
- 現行ハブは「ハブミニ」「ハブ2」「ハブ3」の3種類が存在する
- 機能、性能、操作性の全てで「結論としておすすめはハブ3」である
- ハブ3独自のノブ型コントローラーは日常の直感的な微調整に便利
- ハブの設置には「2.4GHz帯のWi-Fi環境」が必須であるため事前確認を
- Wi-Fiルーターの設定を確認し2.4GHz帯のSSID(ネットワーク名)に接続する
- ハブ導入後の定番追加アイテムは物理スイッチを押す「SwitchBot ボット」
- ボットはリモコンのない家電や照明スイッチを操作できる「指ロボット」
- ハブとボットを連携させることで、外出先からの操作や音声操作が可能になる
- 最終的な理想形は「スマートスピーカー」と連携させたハンズフリー操作
- シーン(定型アクション)設定で「いってきます」の一言で全消灯などが可能
- 導入時はWi-Fiやアカウントのパスワードなどセキュリティ対策を必ず行う
- 火災防止のため電気ストーブなど熱を発する家電の遠隔操作は絶対に行わない




















